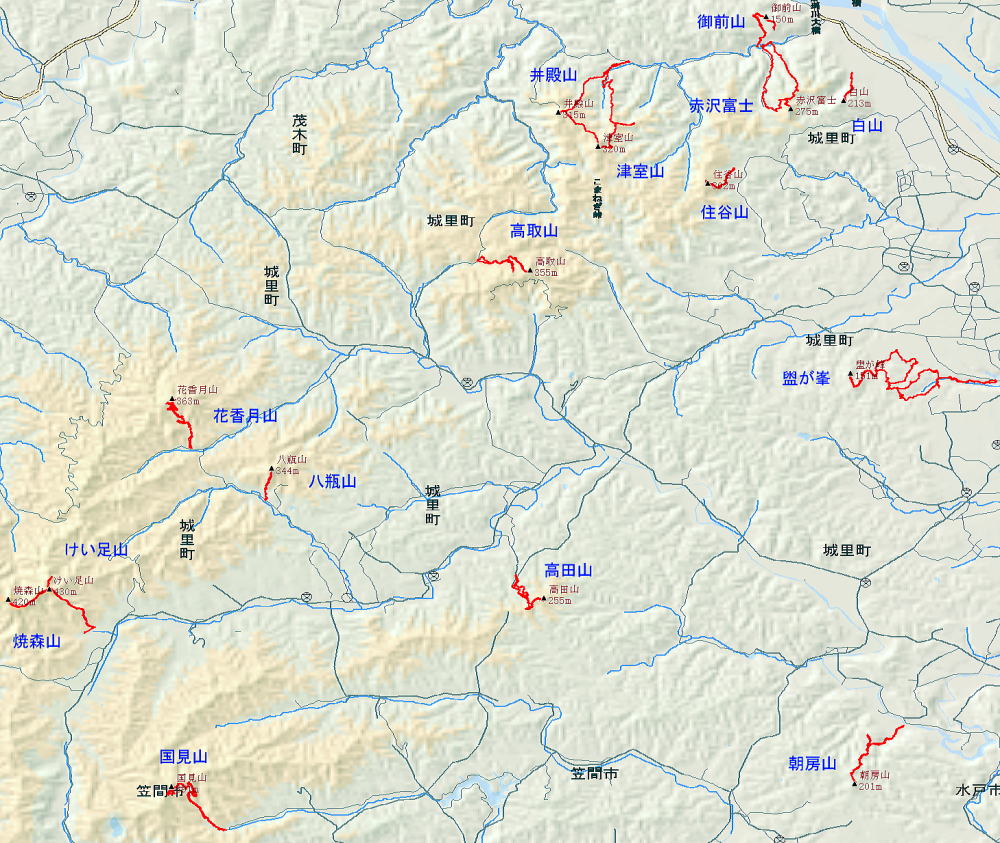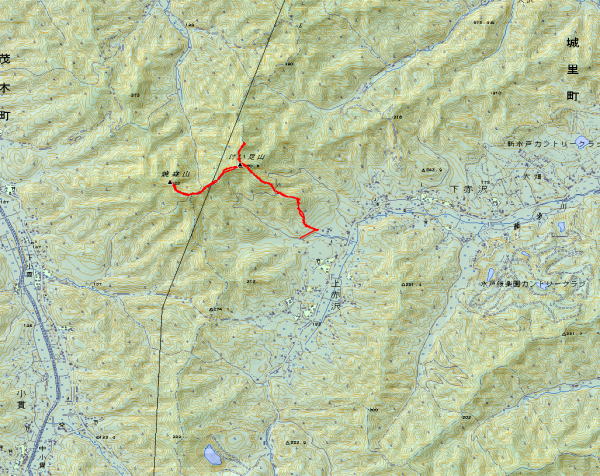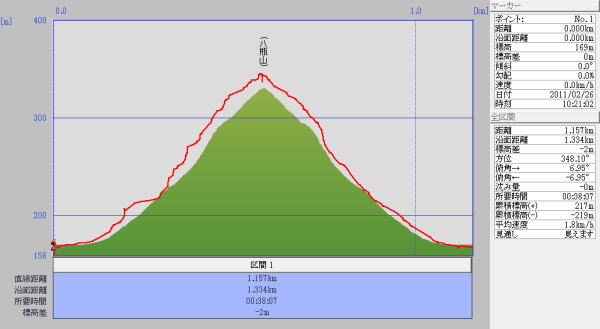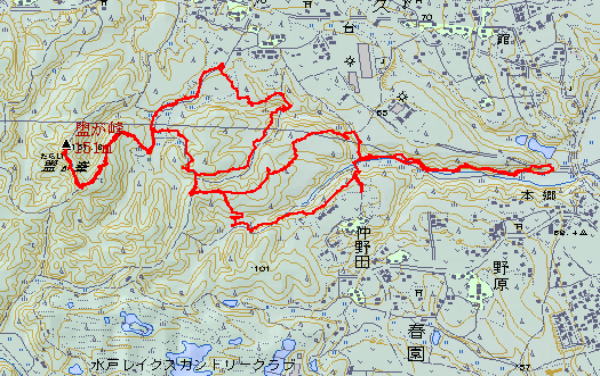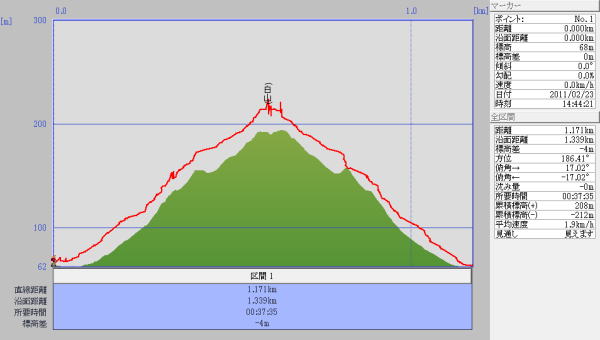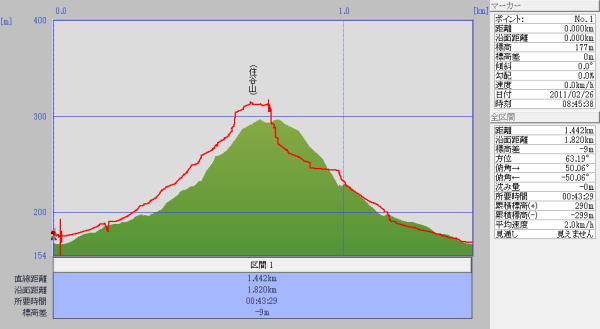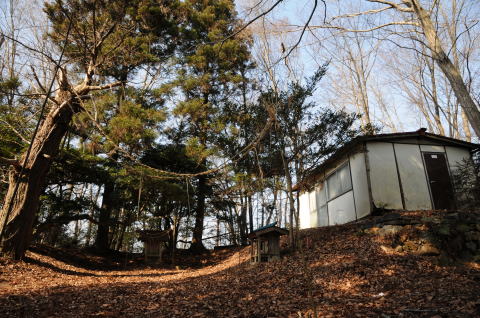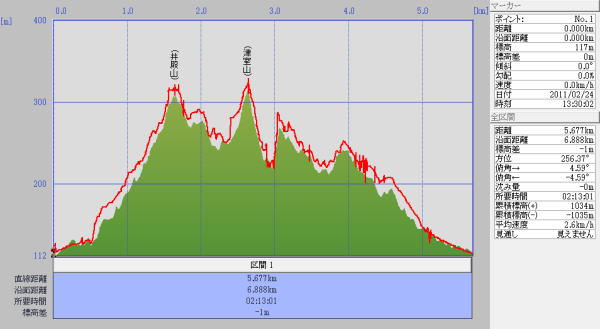|
全山のあらまし
けい足山(標高430.5m) 焼森山(標高420m) H23.1.19
花香月山(標高378.2m) H23.2.26
国見山(標高291.6m) H23.2.26
朝房山(標高201.1m) H23.3.1
盥が峯(標高151.8m) H23.2.23
白山(標高213m) H23.2.23
御前山(標高156m) H23.2.24
高取山(標高355.9m) H23.2.23
このページのトップへ
|